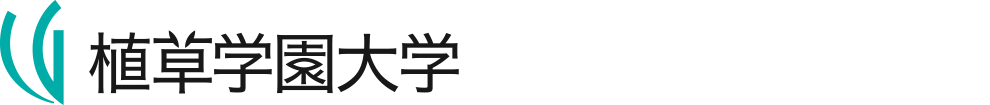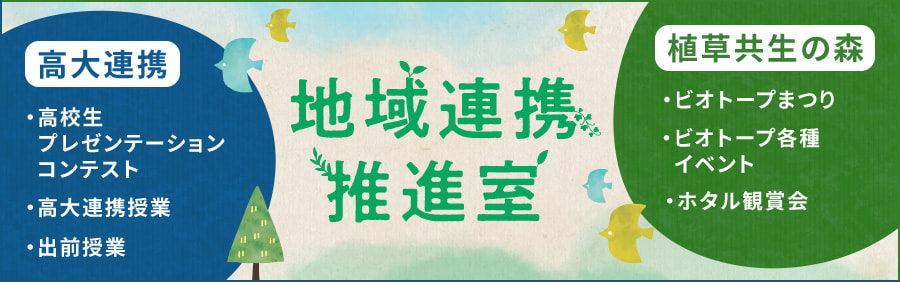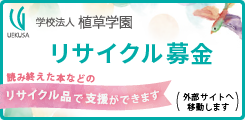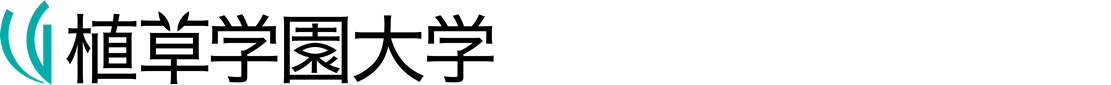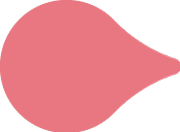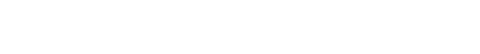学位授与方針及び教育課程編成・実施方針
植草学園大学の学位授与方針及び教育課程編成・実施方針
本学は,発達教育学部,保健医療学部と看護学部の3学部からなる。
発達教育学部には発達支援教育学科,保健医療学部にはリハビリテーション学科があり,看護学部には看護学科がある。
発達教育学部
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
徳育を教育の根幹とする学園建学の精神,学則第1条及び発達教育学部規程第2条に定める教育目的を達成することを基本理念とし,以下に掲げる資質及び能力を身につけ,所定の単位を修得した学生に卒業を認定し,学位を授与する。
- [徳育・教養] 人間や社会に対する理解や生命の尊厳について深く認識し,高い道徳心と倫理観をもって行動できる。
- [共生社会・障害支援] 共生社会の実現をめざし,障害や困難性のある人を支援することができる。
- [社会貢献・地域支援] 関連する諸機関や人々との連携を保ち,地域社会に貢献することができる。
- [科学的・論理的思考] 教育・保育の発展に寄与できる科学的・論理的思考ができる。
- [問題解決・キャリア形成力] 教育専門職・保育専門職として問題を解決し,自ら成長することができる。
- [知識・技能・実践力] 所属するコースの分野について広い視野をもち,正しい知識・確かな技能に基づき実践することができる。
教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)
学位授与方針に掲げる資質・能力を修得させ,教育上の目的を達成するために授業科目を以下の科目の構成,学修内容,学修方法等によって体系的に編成する。
科目の構成と学修内容
- 教養教育科目
基礎科目及び体育スポーツ科目,国際コミュニケーション科目,基礎演習科目を通じて幅広く豊かな教養を身につけ,身体の健康を保ち,コミュニケーション能力を高める。
授業科目「人間と道徳」及び「日本国憲法」を必修科目とする。
基礎演習科目には,初年次教育及びリメディアル教育の内容を含め,大学における学修の基盤を形成する。 - 専門教育科目
学修内容の程度に応じて専門基礎科目と専門科目に区分する。専門分野に従って小学校教育コース,特別支援教育コース,幼児教育・保育コース,発達教育心理コースを設ける。又,学修の体系に応じて必修科目,選択科目の区分を設け,併せて学修の順序に応じて履修学年を指定する。 - 特別支援教育科目
本学部の特長である障害等のある子どもへの支援能力を育成するために,特別支援教育に関する科目を全てのコースにおいて学修するものとする。 - キャリア形成及び主体的学修
社会貢献・地域支援ができる力を育成するため,地域におけるボランティア活動,インターンシップ活動を認定する科目を設け,学生の主体的な学修を支援する。
社会人・職業人として,また特に教育専門職・保育専門職として問題を解決し,自ら成長することができる力を育成するために,キャリア形成を促進するための科目を設ける。 - 専門ゼミナール及び卒業研究
学士課程における学修の専門性を深め,科学的・論理的に課題を分析し,問題解決力を高めるために,必修科目として「専門ゼミナール」及び「卒業研究」を設ける。
学修方法
学内における授業は,講義,演習,実習,実技として行う。これらの授業においては,教育機器やICT技術を用いて,学生の主体的な学修を促し,学修効果を高める。
学外において,学校や施設の見学や実習を行い,職業人としての実践的な能力を高める。
育成する資質・能力等と授業科目との関係
- [徳育・教養] 豊かな人間性に基づく道徳心と高い倫理観をもつ人材を育成することについては,全ての授業科目において留意して教育に当たるとともに,特に「人間と道徳」の授業において建学の精神を含めて学修する。又,教養科目を通じて幅広い教養を身につける。
- [共生社会・障害支援] 所属コースにかかわらず,全ての学生が障害等による困難性のある子どもを支援できる力を身につけるために,特別支援教育に関する科目を指定した単位数修得する。また,共生社会の実現をめざし,インクルーシブ教育システムの観点から,全ての子どもの教育・保育の質の向上及び地域社会の発展に貢献できる力を育成するために,「特別なニーズ教育の基礎と方法」「インクルーシブ保育」の科目を学修する。
- [社会貢献・地域支援] 社会貢献・地域支援できる力を育成するために「社会貢献・地域支援活動Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「インターンシップ活動」の科目を学修する。
- [科学的・論理的思考] 専門領域の知識や理解を深め,科学的思考力・論理的思考力を高めるために,「専門ゼミナール」「卒業研究」などの科目を学修する。
- [問題解決・キャリア形成力] 教育専門職・保育専門職として問題を解決し,自ら成長することができる力を育成するために,「キャリア演習」等の科目を学修する。
- [知識・技能・実践力] 専門科目において育成する知識・技能・実践力については,以下の区分によって科目を構成する。
[小学校教育に関する資質・能力]
- 教科及び教科の指導法に関する科目
- 教育の基礎的理解に関する科目
- 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目
- 教育実践に関する科目
[特別支援教育に関する資質・能力]
- 基礎理論に関する科目
- 知的障害,肢体不自由及び病弱の領域に関する科目
- 前項以外の障害の領域に関する科目
- 教育実践に関する科目
[幼児教育に関する資質・能力]
- 領域及び保育内容の指導法に関する科目
- 教育の基礎的理解に関する科目
- 道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目
- 教育実践に関する科目
[保育士に関する資質・能力]
- 保育の本質・目的に関する科目
- 保育の対象の理解に関する科目
- 保育の内容・方法に関する科目
- 保育実習に関する科目
- 総合演習に関する科目
[発達教育心理に関する資質・能力]
- 発達教育心理に関する科目
学修成果の評価と可視化(アセスメント・ポリシー)
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる資質・能力を以下のように評価し可視化する。
- 学修者評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる1~6の資質・能力について「資質能力自己評価票」に基づいて学生自身が毎年度学修の自己評価を行う。 - 卒業時評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる4と6の資質・能力について,学生個人レベル,学部・学科・コースレベルで卒業研究提出時に行う。学生個人の学修評価は,「卒業研究評価ルーブリック」に基づいて教員が行う。学部・学科・コースの教育評価は,「卒業研究評価ルーブリック」の集計により行う。 - 学修過程評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる2~5の資質・能力についての学修到達状況は,アセスメントツールを用いて,1年時,3年時に学生個人レベル,学部・学科・コースレベルで行う。また,6については学部・学科・コースの教育評価として,年次に応じた資格,免許取得状況,関連の模擬試験,採用試験結果等を参照する。 - 各科目の成績評価
各科目ではシラバスに記載している方法で毎学期の成績評価を行う。学生個人の学修評価としては,修得単位数及びGPA値により評価する。学部・学科・コースの教育評価は履修者数,単位修得者数,GPA値により評価する。なお,学部・学科・コースが編成する授業科目に対しては,授業アンケートにより学生の評価を得る。
その他,学修基礎技能とその評価
授業で育てるレポート,プレゼンテーションなどのスキルなどについては,各スキル評価ルーブリックを用いて評価する。
保健医療学部
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
徳育を教育の根幹とする学園建学の精神,学則第1条及び保健医療学部規程第2条に定める教育目的を達成することを基本理念とし,以下に掲げる資質及び能力を身につけ,所定の単位を修得した学生に卒業を認定し,学位を授与する。
- [徳育・教養] 人間や社会に対する理解や生命の尊厳について深く認識し,高い道徳心と倫理観をもって行動できる。
- [共生社会・障害支援] 共生社会の実現をめざし,障害や困難性のある人を支援することができる。
- [社会貢献・地域支援] チーム医療を発展させると共に関連する諸機関や人々との連携を保ち地域社会に貢献することができる。
- [科学的・論理的思考] リハビリテーションの発展に寄与できる科学的・論理的思考ができる。
- [問題解決・キャリア形成力] 医療専門職として問題を解決し,自ら成長することができる。
- [知識・技能・実践力]
理学療法学専攻:保健・医療について広い視野をもち,理学療法学領域における正しい知識・確かな技能及び知識・技能に基づき実践することができる。作業療法学専攻:保健・医療について広い視野をもち,作業療法学領域における正しい知識・確かな技能及び知識・技能に基づき実践することができる。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
学位授与方針に掲げる知識・技能,資質などを修得させ,教育上の目的を達成するために授業科目を以下の科目の構成,学修内容,学修方法等によって体系的に編成する。
科目の構成と学修内容
- 教養教育科目
大学の理念を学修する科目として「人間と道徳」を必修とする。学部の専門教育科目の基礎知識として「心理学」「人間関係論」「統計学入門」及び「コミュニケーション論」を必修科目とする。
その他の教養教育科目においては幅広い教養を身につけ,体育スポーツ科目においては心身の健康を保ち,国際コミュニケーション科目においてはグローバルコミュニケーション能力を高める。
基礎演習科目においては,初年次教育及びリメディアル教育の内容を含め,大学における学修の基盤を形成する。 - 専門教育科目
基礎医学,臨床医学及び社会医学を学ぶ専門基礎科目と理学療法あるいは作業療法の知識と実践を学ぶ専門科目に区分する。専門分野に従って理学療法学専攻と作業療法学専攻を置く。これらは領域と学修の体系に応じて必修科目,選択科目に区分し,履修の順序に応じて履修学年を指定する。 - 臨床実習科目
専門的職業人としての資質・能力を育成するために,臨床実習科目を置く。これにより臨床における問題解決力及び主体的な学修力を高める。 - 卒業研究
医療専門職として科学的思考の形成及び生涯探究心の育成をめざし,保健医療・リハビリテーションの発展に寄与する卒業研究を必修とする。
学修方法
学内における授業は,講義,演習,実習,実技として行う。これらの授業においては,教育機器やICT技術を用いて,学生の主体的な学修を促し,学修効果を高める。
学外においては医療施設等において臨床実習を行い,職業人としての実践的な能力を高める。
育成する資質・能力等と授業科目との関係
- [徳育・教養] 基本的人権を尊重し,保健・医療・福祉を受ける人の生活感や価値観を理解し,豊かな人間性に基づく道徳心と高い倫理観をもつ人材を育成するために「人間と道徳」を始めとする教養教育科目及び「エレメンタリーセミナー」「生命倫理」などの科目を学修する。
- [共生社会・障害支援] 人間を取り巻く環境と健康,病気,障害へのメカニズムや回復過程を総合的に学び,障害や困難性のある人を支援できる人材を育成するために「解剖学」「生理学」「運動学」「神経学Ⅰ・Ⅱ」「リハビリテーション医学」などの専門基礎科目を学修する。
- [社会貢献・地域支援] 保健医療活動の社会における意義や重要性を理解し,リハビリテーションの地域における役割を修得する。地域理学療法学に関する科目あるいは地域作業療法学に関する科目を学修する。他の医療スタッフとの連携を図る「チーム医療演習」などの科目を学修する。
- [科学的・論理的思考] 科学的根拠に基づき系統立てられている専門基礎科目を学修する。卒業研究により,理論的,研究的能力を養う。「リハビリテーション研究法」「卒業研究」などの科目を学修する。
- [問題解決・キャリア形成力] 保健・医療・福祉の専門職としての問題解決能力及び生涯学習の資質を養い,卒業後の自己研鑽への能力を養う。「臨床実習Ⅲ(総合A,B)」などの科目を学修する。
- [知識・技能・実践力] リハビリテーション専門職としての職業的アイデンティティを育成するために,早期実習を実施し,専門的学習を系統的に学修する。評価学,治療学,生活支援の学理と実践を統合的に学修し,臨床実践能力を養う。臨床実践能力の評価としては,客観的臨床能力試験(OSCE)により客観性を担保して行う。これらの資質・能力を育成するために専攻別に以下の区分によって科目を構成する。
[理学療法士に関する資質・能力]
- 基礎理学療法学に関する科目
- 理学療法管理学に関する科目
- 理学療法評価学に関する科目
- 理学療法治療学に関する科目
- 地域理学療法学に関する科目
- 臨床実習
[作業療法士に関する資質・能力]
- 基礎作業療法学に関する科目
- 作業療法管理学に関する科目
- 作業療法評価学に関する科目
- 作業療法治療学に関する科目
- 地域作業療法学に関する科目
- 臨床実習
学修成果の評価と可視化(アセスメント・ポリシー)
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる資質・能力を以下のように評価し可視化する。
- 学修者評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる1~6の資質・能力について「資質能力自己評価票」に基づいて学生自身が毎年度学修の自己評価を行う。 - 卒業時評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる4と6の資質・能力について,学生個人レベル,学部・学科・専攻レベルで卒業研究提出時に行う。学生個人の学修評価は,「卒業研究評価ルーブリック」に基づいて教員が行う。学部・学科・専攻の教育評価は,「卒業研究評価ルーブリック」の集計により行う。 - 学修過程評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる2~5の資質・能力についての学修到達状況は,アセスメントツールを用いて,1年時,3年時に学生個人レベル,学部・学科・専攻レベルで行う。また,6については学部・学科・専攻の教育評価として,年次に応じた進級評価,実技評価,国家試験結果等を参照する。 - 各科目の成績評価
各科目ではシラバスに記載している方法で毎学期の成績評価を行う。学生個人レベルの学修評価としては,修得単位数及びGPA値により評価する。学部・学科・専攻の教育評価は履修者数,単位修得者数,GPA値により評価する。なお,学部・学科・専攻が編成する授業科目に対しては,授業アンケートにより学生の評価を得る。
その他,学修基礎技能とその評価
授業で育てるレポート,プレゼンテーションなどのスキルなどについては,各スキル評価ルーブリックを用いて評価する。
看護学部
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
徳育を教育の根幹とする学園建学の精神,学則第1条及び看護学部規程第2条に定める教育目的を達成することを基本理念とし,以下に掲げる資質及び能力を身につけ,所定の単位を修得した学生に卒業を認定し,学位を授与するとともに,看護師,保健師(定員あり)の国家試験受験資格を付与する。
- [徳育・教養] 人間や社会に対する理解や生命の尊厳について深く認識し,高い道徳心と倫理観をもって行動できる。
- [共生社会・障害支援] 共生社会の実現をめざし,障害や困難を抱える人を含む,あらゆる発達段階・健康レベルにある人々を支援することができる。
- [社会貢献・地域支援] チームの一員として医療やケアを発展させるとともに,関連する諸機関や人々と連携・協働し,国際的視野をもって,地域社会に貢献することができる。
- [科学的・論理的思考] 課題に対して情報を系統的に収集・分析し,根拠に基づいて科学的・論理的思考ができる。
- [問題解決・キャリア形成力] 問題の解決に対して主体的に取り組み,省察する能力を身に付けることによって,自ら成長することができる。
- [知識・技能・実践力] 看護の専門領域における根拠のある知識・確かな技能に基づき実践するとともに,保健・医療・福祉及び市民と協働することができる。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
学位授与方針に掲げる知識・技能,資質などを修得し,教育上の目標を達成するために授業科目を以下の科目の構成,学修内容,学修方法等によって体系的に編成する。
教養教育科目
- 幅広い視野と思考力・表現力を養うための教養科目
大学の理念を学修する科目として「人間と道徳」を必修とする。幅広い視野と思考力・判断力・表現力を養うために,他の2学部の学生と同じ場で共に学ぶ。4区分を設け,それぞれの区分において,必修・選択の単位を指定する。① 基礎科目では,建学の精神を学修する科目として「人間と道徳」,学部の専門教育科目の基礎知識として「心理学」「社会学入門」「データサイエンス入門」「コミュニケーション論」「障害インクルージョン論」をそれぞれ必修とする。選択科目として人文社会,自然科学,教育学の関連科目を複数置く。
② 体育・スポーツ科目は,スポーツ健康科学基礎理論,体育実技A ~ Dの科目を置き,選択とする。
③ 国際コミュニケーション科目は,「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」を必修とし,その他に「中国語入門」「フ
ランス語入門」「ドイツ語入門」等から選択する。
④ 基礎演習科目は,「情報機器演習」を必修とし,その他に「文章表現演習」「読書技術演習」「自
然科学基礎演習」「海外研修Ⅰ・Ⅱ」から選択する。 - 専門基礎科目
根拠に根差した専門的な判断及び行動のために必要な基礎知識修得のための専門基礎科目を4細区分で構成する。主に必修科目で構成するが,一部選択科目を設ける。① 人体の構造と機能の細区分では,「人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ」「人体の構造と機能演習」「薬理学」「生化学・栄養学」を必修科目として置き,「運動学」「ゲノム・遺伝学」を選択科目として置く。
② 疾病の成り立ちと回復の促進の細区分では,「感染と防御」「病態学」「疾病と治療Ⅰ(内科系疾患)」「疾病と治療Ⅱ(外科系疾患)」「疾病と治療Ⅲ(小児の疾患・感染症)」「疾病と治療Ⅳ(高齢者の疾患・精神疾患)」を必修科目として置く。
③ 健康情報と社会保障制度の細区分では,「保健医療統計学」「保健医療情報学」「公衆衛生学・疫学」「疫学演習」「保健医療福祉制度論」「地域資源とマネジメント」を必修科目として置く。また「医療経済学」を選択科目として置く。
④ 人間と生活・社会の理解の細区分では,「家族社会論」「専門職連携論」を必修科目として置く。「専門職連携論」は他学部との合同授業により行う。 - 専門科目
看護学の基礎から応用発展へと実践的な知識・技術・態度を体系的に修得できるよう専門科目として5細区分を設け,看護の各専門領域及び応用発展領域の科目を1年次から4年次にわたり履修の順序性を考慮して体系的に配置する。1) 看護学の基礎
学問への導入及び専門職業人への志向性を高めるための「エレメンタリーセミナー」,さらに看護学の基本原理・知識・技術の基礎を学ぶための「看護学原論Ⅰ・Ⅱ」「看護基本技術Ⅰ~Ⅲ」「看護基本技術Ⅳ・Ⅴ」「看護倫理」「地域包括ケア論」を必修科目として置く。
2) 健康特性に応じた看護
看護のニーズを健康レベルという観点から系統的に理解できるように,「ヘルスプロモーション」を1年次に,「急性期看護学概論」「慢性期看護学概論」「エンドオブライフケア」「成人(急性・慢性)看護方法Ⅰ」を2年次,「成人(急性・慢性)看護方法Ⅱ」を3年次に置き,全て必修とする。
3) 対象特性に応じた看護
地域・在宅看護学,成人看護学,老年看護学,母性看護学,小児看護学,精神保健看護学の各領域の概論,方法Ⅰ,方法Ⅱ,「健康教育論」を1年次から3年次にかけて系統的に必修科目として学ぶ。また,公衆衛生の視野をもち看護を実践することは今後ますます重要となることから,「公衆衛生看護学概論」を必修科目として2年次に置く。
保健師国家試験受験資格取得者の選択必修科目として,「公衆衛生看護方法論Ⅰ(行政看護)」「公衆衛生看護方法論Ⅱ(学校看護)」「公衆衛生看護方法論Ⅲ(産業看護)」「公衆衛生看護学演習」「地区活動論」を3年次に,「公衆衛生看護管理論」を4年次に置く。
4) 看護学の発展
学修への動機づけ,専門職業人への志向性,研究マインドの醸成を促す科目として「看護学セミナー」「看護学研究Ⅰ」「看護学研究Ⅱ」「看護学研究Ⅲ(卒業研究)」を必修科目として系統的に配置する。地域社会が必要とする看護の開拓及び看護の応用力を学ぶ科目として「災害看護学概論」「グローバルヘルス看護学Ⅰ」「地域共創ケアⅢ」「看護管理・看護政策論」を必修科目として置く。加えて選択科目として「災害看護学演習」「グローバルヘルス看護学Ⅱ」を置く。
5) 臨地実習
実践的な能力を育成するために,多様なケアの場における臨地実習科目を置く。講義・演習と連動させるかたちで運営し,これにより看護の知識・技術・態度を統合し,実践に適用する能力を修得する。必修科目として,1年次及び2年次に,「基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ」「地域共創ケアⅠ・Ⅱ」を配置する。3年次後期に各領域(地域・在宅看護学,成人急性期看護学,成人慢性期看護学,老年看護学,母性看護学,小児看護学,精神保健看護学)の看護学実習を置き,4年次前期に「統合看護実習」を置く。
保健師国家試験受験資格取得者の選択必修科目として,3年次後期に「公衆衛生看護学実習」,4年次前期に「公衆衛生看護展開実習」「公衆衛生看護管理実習」を置く。
専門教育科目
育成する資質・能力等と授業科目との関係
| 区分 | ディプロマ・ポリシー | カリキュラム・ポリシー | |
| 教養教育科目 | 基礎科目 | DP1:[徳育・教養] | CP1:幅広い視野と思考力・表現力を養うための教養教育科目 |
| 体育・スポーツ科目 | |||
| 国際コミュニケーション科目 | |||
| 基礎演習科目 | |||
| 区分 | 細区分 | ディプロマ・ポリシー | カリキュラム・ポリシー | |
| 専門教育科目 | 専門基礎科目 | 人体の構造と機能 | DP4:[科学的・論理的思考] | CP2:根拠に根差した専門的な判断及び行動のために必要な基礎知識修得のための専門基礎科目 |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | ||||
| 健康情報と社会保障制度 | ||||
| 人間と生活・社会の理解 | ||||
| 専門科目 | 看護学の基礎 | DP1:[徳育・教養] DP6:[知識・技能・実践力] |
CP3:看護学の基礎から応用発展へと実践的な知識・技術・態度を体系的に修得するための専門科目 CP4:看護学の基礎 |
|
| 健康特性に応じた看護 | DP2:[共生社会・障害支援] DP6:[知識・技能・実践力] |
CP5:健康特性に応じた看護 | ||
| 対象特性に応じた看護 | DP2:[共生社会・障害支援] DP6:[知識・技能・実践力] |
CP6:対象特性に応じた看護 | ||
| 看護学の発展 | DP3:[社会貢献・地域支援] DP5:[問題解決・キャリア形成力] DP6:[知識・技能・実践力] |
CP7:看護学の発展 | ||
| 臨地実習 | DP6:[知識・技能・実践力] | CP8:臨地実習 | ||
学修成果の評価と可視化(アセスメント・ポリシー)
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる資質・能力を以下のように評価し可視化する。
- 学修者評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる1~6の資質・能力について,「資質能力自己評価票」に基づいて学生自身が毎年度学修の自己評価を行う。 - 卒業時評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる5と6の資質・能力について,学生個人レベル,学部・学科レベルで卒業研究提出時に行う。学生個人の学修評価は,「卒業研究評価ルーブリック」に基づいて教員が行う。学部・学科の教育評価は,「卒業研究評価ルーブリック」の集計により行う。 - 学修過程評価
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる1~6の資質・能力についての学修到達状況は,客観的評価ツールとしてGPS-Academicを用いて,1年時,3年時に学生個人レベル,学部・学科レベルで行う。また,学部・学科の教育評価として,年次に応じた進級評価,関連の模擬試験,国家試験結果等を参照する。 - 各科目の成績評価
各科目では,シラバスに記載している方法で毎学期の成績評価を行う。学生個人レベルの学修評価としては,修得単位数及びGPA値により評価する。学部・学科の教育評価は履修者数,単位修得者数,GPA値により評価する。なお,学部・学科が編成する授業科目に対しては,授業アンケートにより学生の評価を得る。
その他,学修基礎技能とその評価
授業で育てるレポート,プレゼンテーション等のスキルについては,各スキル評価ルーブリックを用いて評価する。