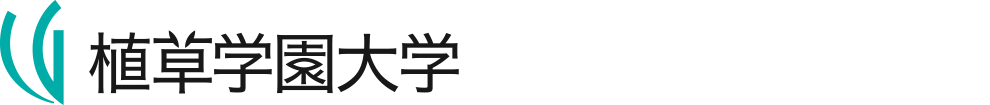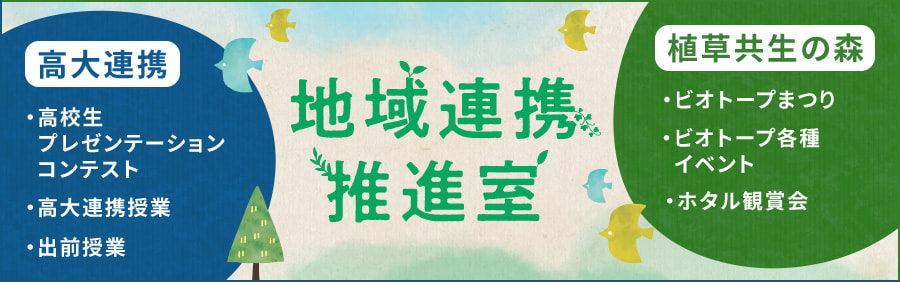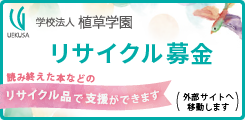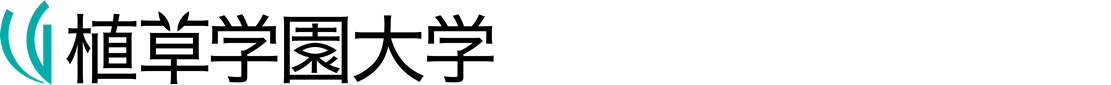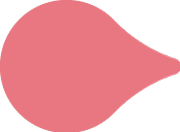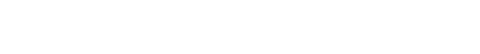高大連携授業 7月15日(月)の受講生を募集します
2019.06.28(7年前)
植草学園入試・広報課
高校生のみなさんに大学・短大の授業を体験してもらうため、7月15日(月)2限・3限の受講生を募集します。
将来、小学校・特別支援学校・幼稚園の先生、保育士、理学療法士、作業療法士になりたい高校生のみなさん!大学・短大教育の実際、大学生活を体験できるチャンスです。
大学・短大の枠を越えて受講できますので、関心のある分野の授業に参加してください。
自分が受けたい授業をクリックして、詳細を確認しお申し込みください。
募集期間
| 令和元年6月10日(月)~20日(木) | 植草学園大学・短期大学との高大連携校、附属高校の生徒さん対象 (若松・佐倉東・八街・四街道・松尾・成東・大多喜・木更津・君津・京葉・佐倉西・千城台・船橋二和・船橋古和釜・土気・実籾・佐倉南・四街道北・富里・千葉黎明・東京学館・桜林・植草学園大学附属)※高等学校コード順 |
|---|---|
| 令和元年6月26日(水)~7月5日(金) | 千葉県内外高校全生徒さん対象 |
7月15日(月)時間割
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 小学校教育
- 授業名
- 文章表現演習
戸丸 俊文
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
教授

大学生活で必要とされるレポートの書き方や実用的な文章の作り方を15回の授業を通して学びます。
今回は、広告文の作り方を学びます。
Web広告・チラシ等、私達の生活は広告にあふれています。効果的な広告の文章はどのようにすれば書けるのか、広告文の基礎的な技術について学びます。
また、文章表現力向上のためには、情報の収集・整理等の力をつけていくことと、さまざまなな角度から事象を考えられる発想訓練も必要となっていきます。その点にも少し触れていきたいと思います。
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 幼児・保育
- 授業名
- 専門ゼミナールⅡ
森高 光広
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
教授
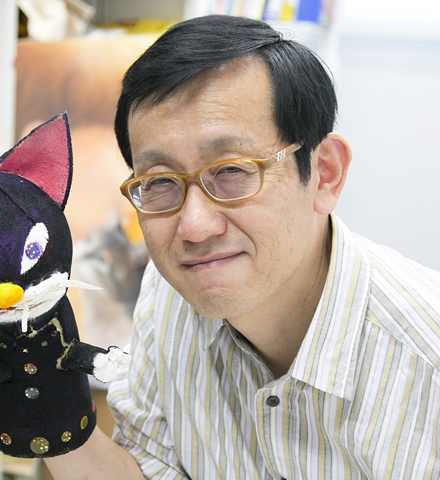
 幼児・保育専攻の学生が、造形活動を通して人と関わりながら、たくさんのことを学ぶ研究室(4年生)の授業です。
幼児・保育専攻の学生が、造形活動を通して人と関わりながら、たくさんのことを学ぶ研究室(4年生)の授業です。
学生がこの授業で学んできたことや卒業研究をどのように考えているか、みなさんにプレゼンします。
その後、ゼミ学生5名がそれぞれ高校生にもできる造形ワークショップを開きます。実際に制作しながら大学の学修や生活のことを聞いてください。造形ワークショップは1グループ3・4名、内容は手先の器用さや得手・不得手関係なく60分程度で楽しく制作できるものを学生が用意します。例えば、紙粘土制作やポップアップカードなどです。
保育士・幼稚園の先生に関心のある方や植草学園の幼児・保育専攻の学びに興味のある方は気軽に参加してください。
定員になりましたので、受付を終了しました
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 理学療法
- 授業名
- 理学療法評価学実習Ⅱ
千葉 諭
植草学園大学
保健医療学部
理学療法学科
助教

身体が硬い・柔らかいという言葉を耳にする機会があると思いますが、みなさんは「身体の柔らかさ」をどう判断していますか?
理学療法士は、「硬い・柔らかい」という主体的な言葉ではなく、客観的なデータを示して情報を共有します。さまざまな所見を客観的な指標で判断することを「評価」といいます。
今回の授業では、実際に「評価」というものを体験してもらいます。いろいろなストレッチを経験してもらい、ストレッチ後に身体が柔らかくなった、ということを評価してもらいます。
*身体を動かす実技を多く取り入れますので、ジャージやハーフパンツなど、動きやすい服装でお越しください。
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 保育
- 授業名
- 子どもと言葉保育教材を使って
植草 一世
植草学園短期大学
福祉学科
児童障害福祉専攻
教授
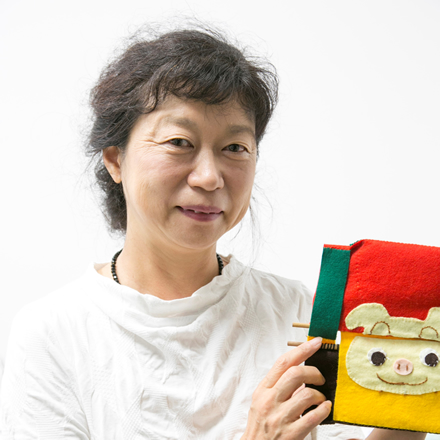
 大学・短大が同時進行で行っている授業「保育内容(言葉の指導法)」の一部に参加してもらいます。
大学・短大が同時進行で行っている授業「保育内容(言葉の指導法)」の一部に参加してもらいます。
この授業は、入学して3ヶ月の1年生が対象です。
これまでの授業では子どもと言葉の意味を学び、子どものための絵本や紙芝居、パネルシアター等の教材やその指導法を学んできました。これまで学生たちはグループで話し合い、教材を作ってきました。今回は、ミニシアターを発表することになっています。高校生のみなさんは、4・5歳くらいの子ども役になって、学生のミニシアターを楽しんでください。
授業の前後は、高校生のみなさんだけでパネルシアター作り体験をしてみましょう。
*カラーペンで絵を描きます。汚れても大丈夫な服装でお越しください。
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 特別支援教育
- 授業名
- 専門ゼミナールⅠ
渡邉 章
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
教授

 障害等により特別なニーズのある子どもへの支援について学びます。少人数による演習形式の授業です。
障害等により特別なニーズのある子どもへの支援について学びます。少人数による演習形式の授業です。
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 一般教養
- 授業名
- 英語Ⅰ
長谷川 修治
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
教授

①英字新聞や英文雑誌(TIME)の英語を学ぶ:日常生活で遭遇する書き言葉のうち、教養のある人々が読む新聞や雑誌に出現する英語の実物を見ることにより、学校で習う英語だけではカバーできない「使える英語」を修得するための訓練をします。
②映画(The Sound of Music)の英語を学ぶ:高校レベルの語彙でなんとか理解が可能な話し言葉のうち、身近な教材として活用できる映画を観ながら、知識として知っている単語や表現の使用方法をリスニング力とともに修得する訓練をします。
③ 英語の対話・表現活動をする:学生がペアになり、修得した英語の語彙や表現を使用して、定型的な対話から個別の表現活動ができるように訓練をします。
*筆記用具持参
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 幼児・保育
- 授業名
- 専門ゼミナールⅠ
金子 功一
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
講師

「専門ゼミナール」では、保育現場で活躍できる保育教諭をめざすために、学生同士の交流を通して専門的な技術を高めたり学びを深めたりしています。
「専門ゼミナールⅠ」では、保育教諭をめざす3年生9名が在籍しており、さまざまな活動を行っています。今回は高校生のみなさんが楽しめるように実際の保育の魅力を一緒に体験したり語り合ったりしていきましょう♪植草学園大学の学生との交流も楽しんでくださいね☆
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 理学療法
- 授業名
- 日常生活活動学実習
角 正美
植草学園大学
保健医療学部
理学療法学科
講師
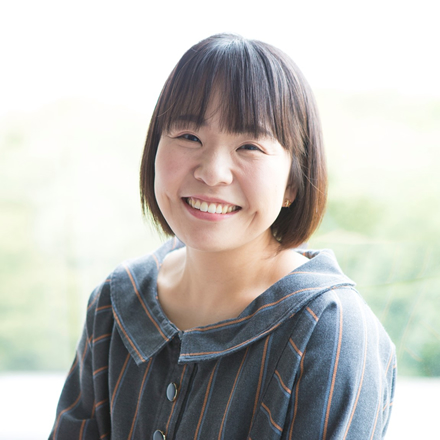
日常生活活動(activities of daily living:ADL)とは、朝目覚めて夜眠りにつくまでの間に、誰もが行うごく基本的な身の回りの動作のことをさします。
例えば、食事や入浴、歩いたり、階段を上ったりする動作のことです。思わぬ病気や事故、加齢による変化から、ADLの中で、不便なことやできないこと、人に頼みたいな…と思うことが出てきます。理学療法士は、痛みを和らげたり、適切な筋力トレーニングを指導したり、効率の良い身体の動かし方を伝えたりすることで、患者さんのADL遂行能力を向上させるお仕事です。日常生活活動学実習では、病気の特徴を理解し、その特徴に合わせたADL指導法を学んでいます。
*寝返りや歩行の練習などもあるので、動きやすい服装でお越しください。
高大連携授業(2019年7月15日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 保育 特別支援教育
- 授業名
- インクルーシブ保育Ⅰ「発達障害を考える」
佐藤 愼二
植草学園短期大学
福祉学科
児童障害福祉専攻
教授

今、どの幼稚園・保育所にも障害のある子ども、「気になる」子どもが在園しています。
この授業では、「発達障害」という大変わかりにくく、誤解されやすい(=努力不足…身勝手…わがまま……)障害について疑似体験等も踏まえて考えながら、どの子どもも包み込むインクルーシブ保育の在り方を考えます。
授業の合間には、どの子どももひきつける、楽しく・うれしい「手遊び」、「マジック」等にもチャレンジしましょう!なお、本授業は高校生のみなさんだけを対象とする特設授業になります。
 |
 |
お申し込みは終了いたしました