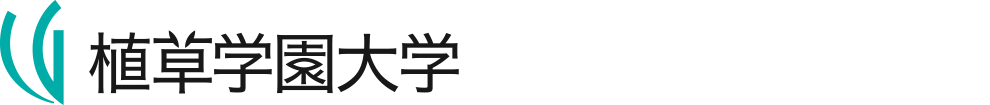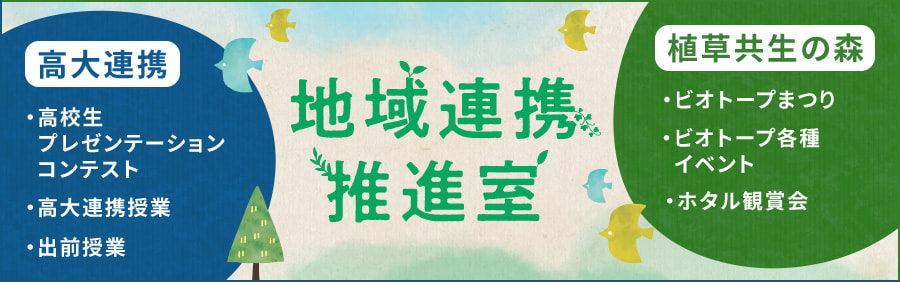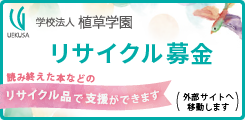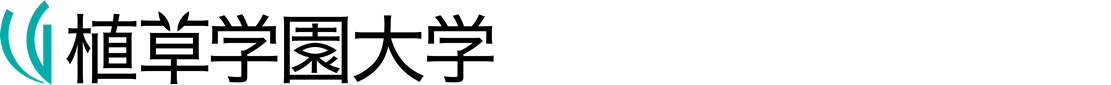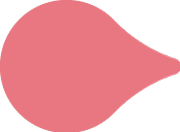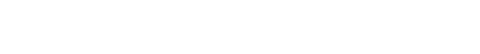高大連携授業 9月23日(月祝)の受講生を募集します
2019.08.26(6年前)
植草学園入試・広報課
高校生のみなさんに大学・短大の授業を体験してもらうため、9月23日(月祝)2限・3限の受講生を募集します。
将来、小学校・特別支援学校・幼稚園の先生、保育士、理学療法士、作業療法士になりたい高校生のみなさん!大学・短大教育の実際、大学生活を体験できるチャンスです。
大学・短大の枠を越えて受講できますので、関心のある分野の授業に参加してください。
自分が受けたい授業をクリックして、詳細を確認しお申し込みください。
募集期間
| 令和元年8月26日(月)~9月5日(木) | 植草学園大学・短期大学との高大連携校、附属高校の生徒さん対象 (若松・佐倉東・八街・四街道・松尾・成東・大多喜・木更津・君津・京葉・佐倉西・千城台・船橋二和・船橋古和釜・土気・実籾・佐倉南・四街道北・富里・千葉黎明・東京学館・桜林・植草学園大学附属)※高等学校コード順 |
|---|---|
| 令和元年9月10日(火)~9月18日(木) | 千葉県内外高校全生徒さん対象 |
9月23日(月祝)時間割
2時限11:00~12:30
3時限13:20~14:50
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 保育
- 授業名
- 幼児教育相談の基礎
桑田 良子
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
講師
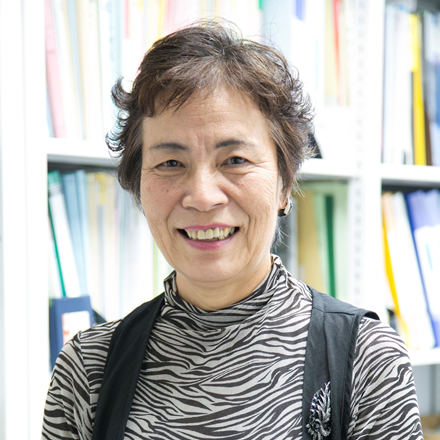
保育士、幼稚園教諭の主たる仕事は、子どもや保護者の気持ちに寄り添い、子どもの発達を支援することです。そのために必要な専門的知識や基礎的技術を15回の授業を通して学びます。
今回はその第1回目ですので、導入の時間になります。相談(カウンセリング)の技術の必要性を社会的背景から考えるとともに「人の話を聴く」「聴いてもらう」時の心の動き、気持ちの変化を体験から学びます。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 保育
- 授業名
- 保育内容演習Ⅱ(環境)
奥村 幸子
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
講師

子どもは身近な環境に能動的に関わり、その充実した活動すなわち“遊び”を通して心身の成長が可能となります。それを遊びを通しての学びと呼んでいます。
子どもたちは、遊んだり生活したりする幼稚園の中で、文字や標識とどのように関わっているのでしょうか。本日の授業では、文字や標識について映像を通して考え、体験していきたいと考えています。
○ガイダンス
○8・9月の幼稚園の子どもたちの遊びや生活の様子を映像を通して見ていく
○園生活の中で、簡単な標識や文字などに関心をもつ
・文字に親しむ(活動1 新聞で遊ぼう)
・標識の意味を理解する(活動2 身近な環境の中で、標識を見つけよう)
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 基礎医学 リハビリテーション
- 授業名
- 生理学実習
桑名 俊一
植草学園大学
保健医療学部
理学療法学科
教授

私たちの体の筋や神経は電気信号を使って情報を伝え合っています。これらの電気活動を体表面から記録したものが、筋電図、心電図、脳波になります。本授業では、実際に腕の筋肉を収縮させて筋電図を記録してみます。また、神経を電気刺激して、筋肉が収縮することを観察します。
*上腕を露出できる半そでシャツで参加してください。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- リハビリテーション
- 授業名
- 作業療法学概論
山崎 郁子
植草学園大学
保健医療学部
講師

作業療法と理学療法はリハビリテーション医療を実践する上で中心的な役割を果たしています。作業療法の目的は、「身体障害者と精神障害者の応用動作能力と社会的適応能力を回復させること」です。そのために作業療法士は、手工芸、芸術、遊び、スポーツなどを通してリハビリを行います。この授業では作業療法の概要や手法について学修します。今回は、特に「音楽療法」を体験します。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
2限
- 分野
- 特別支援教育
- 授業名
- 言語障害教育
堀 彰人
植草学園短期大学
福祉学科
児童障害福祉専攻
教授
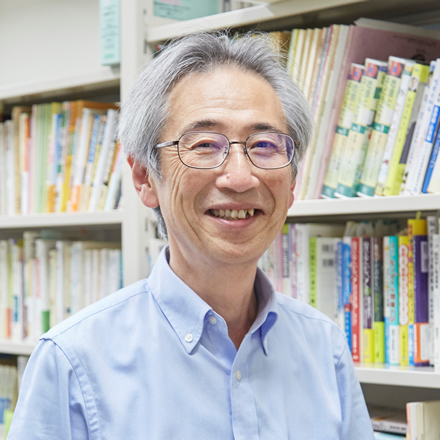
幼児教育、保育の場で出会うことの多いことばの問題について基本的な対応の仕方などについて学びます。さらに、このような子どもたちに対して小学校の「ことばの教室」などで行われる相談や支援の一端について、実技も含めて紹介していきます。
*手鏡などがあれば持参してください。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 教育・保育
- 授業名
- 教育原理
髙野 良子
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
教授

教材として『「かくれんぼ」ができない子どもたち』を使います。なぜ、かくれんぼができないのでしょうか。授業で考えてみましょう。
子どもの遊びは変わってきています。「三間(さんま)」が喪失している(時間、空間、仲間:遊ぶ時間や場所が失われ、友だちがいなくなったこと)と言われています。第1回目では、このような遊びや生活の変化を切り口にして、「消えゆくHB」「朝食と成績の相関」「10のコ食(こしょく)」などをデータに基づき、グループで話し合います。
教育の原理や理論の学修に入る前に、現代の教育・保育分野のさまざまな事象や課題を取り上げ、子どきもたちのおかれている複雑に入り組んだ現代社会を読み解き、変動する社会の中の子どもの姿を探ってみましょう。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 保育
- 授業名
- 幼児・児童の病気と医療
栗山 敦子
植草学園大学
発達教育学部
発達支援教育学科
講師

生まれたばかりの赤ちゃんは小さくて弱々しい印象を受けます。特に人間の赤ちゃんは、他の動物の赤ちゃんに比べて一層頼りない存在です。実際、か弱い子どもはよく病気にかかります。にもかかわらず、子どもはからだの不調を言葉で十分に伝えることもできません。例えば「頭が痛い」といえるのは4歳ころからといわれています。また、子どものからだは大人のミニチュアではなく、からだの働きも異なります。鼻がつまると大人は口で呼吸し、さほど苦しくありませんが、子どもはそうはいきません。このようにいろいろな点で大人と違う子どもを理解し、病気のサインを見逃さないようにするにはどうしたいいのでしょうか。授業初回の今回は①子どものかかりやすい病気、②病気からからだを守る「免疫」の仕組み、③子どもの病気のサインについてお話してみようと思います。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 理学療法基礎
- 授業名
- 運動学Ⅰ
三浦 達浩
植草学園大学
保健医療学部
理学療法学科
教授

理学療法士は患者さんの運動障害を改善させます。運動学はその際に必要な基礎知識であり治療の基盤となるものです。異常な運動を見極めてその原因を分析するためには、正常な運動について知る必要があります。運動学では、解剖学や生理学で学修した骨・関節・靭帯・筋の構造や機能を復習し、筋と関節運動の関係(筋の作用)を学びます。それによって、身体を動かしているときに使用している筋やその使い方を推定できるようになります。今回の授業は「運動学Ⅰ」の第1回目ですので、まず、関節運動を表す用語に関わる基礎を学びます。
高大連携授業(2019年9月23日(月)開催)のご案内
3限
- 分野
- 保育
- 授業名
- 保育の表現技術Ⅱ(身体表現)
松原 敬子
植草学園短期大学
福祉学科
児童障害福祉専攻
教授

子どもは、遊びを通してさまざまなことを学び、多くのことを吸収し、遊びによって成長していきます。特に、運動遊びは子どもの心を解放し、調整力が高められます。今回は、タオルを使った遊びを体験しましょう!! 友だちと関わる楽しさや集団で遊ぶダイナミックさを味わい、友だちとのつながりや仲の深まりを大切にしていきます。幼な心に戻って、無邪気に遊びましょう!!
*動きやすい服装で参加してください。
*フェイスタオル(普通版)・上履き・飲み物を持参してください。
当日は、学生食堂を学生料金で利用できます。
メニューはお楽しみに!
 |
 |
 |
お申し込みは終了いたしました