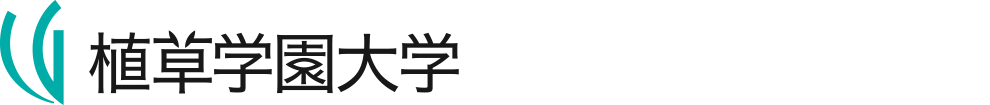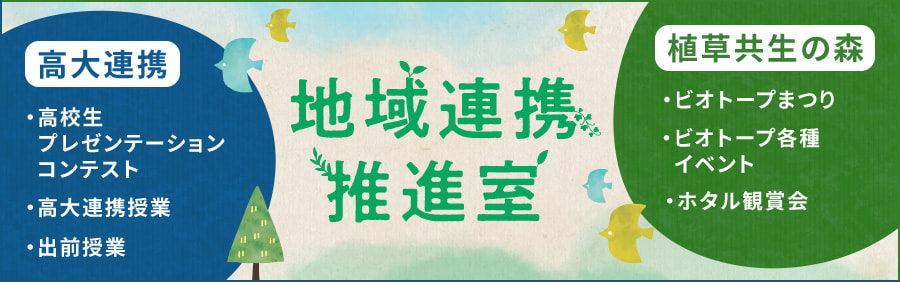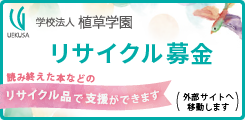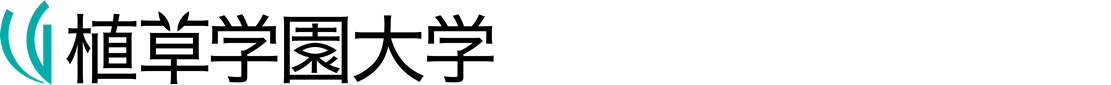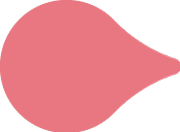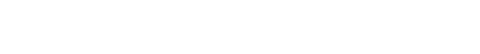「音楽を聴いて色と形で表現する活動」
―発達教育学部 幼児教育・保育コース「子どもと表現」の授業を紹介します!―
2024.11.19(1年前)
植草学園入試・広報課
「音楽を聴いて色と形で表現する活動」
―発達教育学部 幼児教育・保育コース「子どもと表現」の授業を紹介します!―
発達教育学部 教授 高木夏奈子
発達教育学部の幼児教育・保育コースでは、保育者養成課程における「表現」の領域の学修として1年次に「子どもと表現」と学びます。この科目は、それぞれ音楽・造形・身体表現を専門とする3人の教員がオムニバスで行っています。
音楽の授業回で、「音楽を聴いて色と形で表現する活動」を行いました。通常、「音楽は耳で聴くもの」と考えがちですが、太鼓の音の振動は身体で感じますし、「音色」「柔らかい音」「温かい音」など、音を表現する言葉は五感にわたっています。A-A-B-Aで構成される〈シンコペーテッド クロック〉(アンダソン作曲)の冒頭1分ほどを繰り返し聴いて、音楽を聴いて抱いたイメージを台紙に色紙を切り貼りして表現しました。台紙の左側がA、右側がBを表現したものです。台紙の上部に、ABそれぞれにタイトルもつけました。表現活動に「正しい」「間違い」はありません。子どもの表現に寄り添って共に表現を楽しめる保育者に育ってほしいと願っています。

【授業後のコメント】
音楽を聴いて造形で表すと、みんな想像するものは違っても、イメージの雰囲気は似ていて面白いと思いました。Aの部分は朝のイメージを持ったり明るい色を使う人が多く、Bの部分では夜のイメージを持ったり暗い色を使う人が多かったです。色々な人の作品を見て、「そんな表現方法があったんだ! なるほど」という発見や学びがたくさんありました。(1年生 K・Mさん)
「子どもと表現」(音楽)の締めくくりである第5回の授業では、クラシック曲を聴き、曲の雰囲気を自分なりにくみ取り、折り紙で切り貼りして表現するという活動を行いました。同じ曲でも人によって雰囲気の感じ方、折り紙の使い方、表現の仕方は様々であり、この活動はその人の性格、考え方がよく表れるものだったのではないかと思いました。この活動を通し、人の感性の違いを強く感じるとともに、想像力豊かな子ども達が同じ活動に取り組んだら、学生では見られなかった作品が多く生まれ、新たな発見をすることが出来るのではないかと思いました。(1年生 N・Tさん)